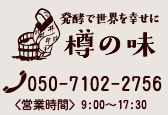いぶりがっこで健康生活!罪悪感なく美味しく楽しむ食べ方ガイド
秋田名物のいぶりがっこは、その独特の風味と食感で多くの人を虜にしている発酵食品の漬物のです。
しかし、「発酵食品だから体にいいって聞くけど、塩分やカロリーは大丈夫?」と、健康への影響が気になっている方もいるのではないでしょうか。
ここでは、いぶりがっこを「健康的に、そして罪悪感なく」楽しむための具体的な方法をご紹介します。
いぶりがっこってヘルシーなの?気になるカロリー・糖質・塩分量を徹底解説!
いぶりがっこにはカロリーや糖質、特に塩分はどのくらい含まれているのでしょうか?
健康を意識する上で、これらの数値は非常に重要です。ここでは、いぶりがっこの具体的な栄養成分を明らかにし、あなたが抱える疑問を解消していきます。
いぶりがっこのカロリーと糖質は意外と控えめ
いぶりがっこは大根を燻製にして漬け込んだ発酵食品ですが、そのカロリーと糖質は意外と控えめです。
理由としては、主原料である大根が低カロリー・低糖質な野菜なのと、製造過程で余分な糖分が加えられることも少ないため、一般的なおやつや加工食品に比べても安心して食べられます。
例えば、一般的な市販のいぶりがっこ100gあたりのカロリーは約50〜70kcal、糖質は約8〜10g程度と言われています。
これは、白米お茶碗半分程度のカロリーに相当し、適量であれば糖質制限中の方でも取り入れやすい数値と言えます。
気になる塩分量は適量を守れば問題なし
いぶりがっこは大根の保存性を高めるために塩漬けにする工程があるため、塩分はやや高めですが他の漬物と比べて極端に高いわけではないので、適量を守って食べることが重要ですが、いぶりがっこはぱりぱりとした食感なので、よく噛んで食べる分少量でも満足感があり、一度に大量に食べる人は少ないでしょう。
とはいっても、美味しい漬物なので、「ついつい」と食べ過ぎてしまわないように注意が必要です。
健康効果の秘密は「乳酸菌」と「食物繊維」
いぶりがっこが健康に良いとわれるのは、「カロリーや糖質が低いから」だけではありません。
豊富な「植物性乳酸菌」と「食物繊維」が含まれているのも大きな理由です。
これらは、大根が発酵する過程で生成され、漬物ならではの栄養素として注目されています。
植物性乳酸菌は、腸内環境を整え、免疫力向上に役立つことが知られています。
また、食物繊維は、便通を改善し、コレステロール値の低下にも寄与すると言われています。
これらの相乗効果によって、いぶりがっこは単なるおつまみ以上の健康効果が期待できる食品なのです。
【シーン別】いぶりがっこを罪悪感なく楽しむ食べ方
いぶりがっこを楽しく、美味しく食生活に取り入れていくための具体的なアイデアをご紹介します。
せっかく食べるなら罪悪感なく、そして楽しくに美味しくたべたいですよね。
ここでは、様々なシーンに合わせたいぶりがっこの賢い食べ方をご提案します。
お酒のおつまみにするなら?減塩おつまみアイデア
お酒を飲むときに、ついつい手が伸びてしまうのが塩辛いおつまみですが、いぶりがっこは工夫次第でヘルシーなおつまみに変身させることができます。
そもそも、いぶりがっこ自体がしっかりとした風味を持つため、少量でも満足感が得られ他の高カロリーなスナックに頼る必要がなくなります。
また、いぶりがっこをチーズやナッツなど、栄養価が高く塩分を排出する作用のあるカリウムを含む食材と組み合わせることで、塩分の過剰摂取を抑えつつ、満足度を高めることができます。
また、いぶりがっこをクリームチーズと合わせるのは定番ですが、アボカドやオリーブオイルと和えても美味しいです。
さらに、細かく刻んでポテトサラダに混ぜ込んだり薄切りのハムで巻いたりして他の具材と組み合わせれば、いぶりがっこの量を減らしつつ、いぶりがっこを楽しめるおつまみになります。
ご飯のお供に!満足感を高める賢い組み合わせ
ご飯のお供にいぶりがっこを食べるのは日本ならではの楽しみ方ですが、量と組み合わせを意識することでより健康的になります。
これは、いぶりがっこが少量でもご飯を進ませる強い風味を持っているため、ご飯の量を減らしても満足感が得られやすいからです。
また、食物繊維が豊富な海藻類や、タンパク質が摂れる卵などと組み合わせることで栄養バランスが向上し、血糖値の急上昇を抑える効果も期待できます。
例えば、細かく刻んでご飯に混ぜ込んでおにぎりにする際は、ワカメやひじきなどの海藻を一緒に混ぜると食物繊維を補給できます。
また、卵かけご飯にいぶりがっこを添えたり、味噌汁の具材として少量加えるのも全体の塩分を調整しながら美味しく楽しむための賢い方法です。
小腹が空いた時やもう一品欲しい時に!手軽に栄養チャージ
少し小腹が空いた時や、食卓にもう一品加えたい時にも、いぶりがっこは手軽に栄養をチャージできる便利な存在です。
いぶりがっこはそのまま食べられる手軽さがあるため、お菓子やジャンクフードに食べる代わりにいぶりがっこを食べれば、発酵食品としての乳酸菌や食物繊維を手軽にとりいれつつお菓子やジャンクフードよりカロリーや糖分を抑えることができます。
スティック状にカットしたいぶりがっこをそのまま食べるのも良いですが、無糖ヨーグルトに少量刻んで入れたりサラダのトッピングとして加えたりすると健康的に美味しく食べれます。
また、野菜スティックと一緒にディップ感覚で添えるのも、満足感がありながらヘルシーに楽しめる方法のひとつです。
いぶりがっこの栄養を最大限に引き出す!もっと美味しく健康に食べるコツ
いぶりがっこをただ食べるだけでなく、せっかくならその栄養価を最大限に活かして、もっと美味しく、そして健康的に楽しみたいですよね。
ここでは、いぶりがっこが持つ健康パワーを効率よく引き出し、毎日の食卓に賢く取り入れるためのちょっとしたコツをご紹介します。
植物性乳酸菌を効果的に摂るには「生」で食べるのがおすすめ
いぶりがっこに含まれる植物性乳酸菌は、熱に弱い性質があるため、生で食べることが最も効果的です。
乳酸菌は、加熱調理することでその多くが死滅してしまうため、せっかくの腸活効果を損なってしまう可能性があります。
そのため、いぶりがっこ本来の風味と栄養を損なわずに摂取するには、加熱せずそのままいただくのが最適です。
例えば、細かく刻んでサラダのトッピングにしたり、クリームチーズなどと合わせてカナッペにしたりする食べ方や、おつまみとしてそのままカットして食べる食べ方は、加熱せずに乳酸菌をそのまま摂れる理想的な食べ方です。
食物繊維と乳酸菌の相乗効果で腸活を加速させる
いぶりがっこに含まれる食物繊維は腸内の善玉菌のエサとなり、乳酸菌は善玉菌そのものなので、この2つの成分同時に取り入れ相乗効果を期待します。
具体的には、いぶりがっこと一緒に、水溶性食物繊維が豊富な海藻類(わかめ、昆布など)やきのこ類、根菜類などを組み合わせると良いでしょう。
また、いぶりがっこを刻んでひじきの煮物と混ぜたり、きのこたっぷりのスープにいぶりがっこを添えたりすると、美味しく取り入れることができます。
身体を温める食材と組み合わせて代謝アップ
いぶりがっこは冷たいまま食べることが多いですが、身体を温める食材と組み合わせることもおすすめです。
冷たい食べ物ばかり摂ると、身体が冷えやすくなり代謝が落ちる可能性がありるので、発酵食品であるいぶりがっこに、身体を温める作用のある食材を加えた料理もおすすめです。
いぶりがっこと生姜の千切りを和えたり、唐辛子を少し加えたピリ辛の炒め物にいぶりがっこを入れるのもおすすめですし、温かい味噌汁の具材として少量加えるのも、身体を温めつつ栄養を摂れる良い食べ方です。
無添加・無着色にも注目!身体に優しいいぶりがっこの選び方
添加物や着色料を気にされる方は、いぶりがっこを選ぶ時にも注目する必要があります。
せっかく身体に良いものを食べるなら余計な添加物は避けたいですよね。
ここでは、安心して美味しくいぶりがっこを楽しむためのポイントをご紹介します。
「無添加・無着色」表示でより自然な味わいを
いぶりがっこを選ぶ際は、「無添加・無着色」と表示されているものを選ぶのがおすすめです。
「無添加・無着色」ということは、余計な保存料や着色料が使われていないので、大根本来の風味やいぶりがっこの自然な味わいを楽しむことができるからです。
また、化学的な合成添加物を避けたいという健康志向の高い方でも、安心して食べれるポイントとなります。
「無添加・無着色」を確認するには、商品のパッケージ裏面にある原材料表示を確認し、よく分からないカタカナ表記名前が沢山書いてあったり「着色料」なども文字が沢山ある商品はなるべく避け、「大根、米ぬか、塩、砂糖(少量)」など、シンプルな原材料で構成されているかを選びます。
こうやって、少し意識する事でより自然に近い製法で作られている商品を購入する事ができます。
原材料と製造方法で選ぶ!「いぶりがっこ」本来の美味しさ
いぶりがっこ本来の美味しさを重視するなら、原材料となる大根の品質や、伝統的な製造方法にこだわっているかをチェックしましょう。
質の良い大根を使用し、昔ながらの燻製と米ぬかを使った製法で作られているいぶりがっこは風味豊かで栄養価も高くなります。
大量生産品の中には、短期間で風味を出すために燻製液を使用したり発酵期間を短縮したりしているものもあるため、信頼できるメーカーや産地の情報が明確に記載されている商品を選ぶのが賢明です。
例えば、「秋田県産大根使用」「〇〇(地域名)の伝統製法」といった記載があるものは、品質にもこだわっている可能性が高いです。
減塩タイプも選択肢に!健康を意識した商品選び
特に塩分摂取を気にしている方は、「減塩タイプ」のいぶりがっこも選択肢に入れるのをおすすめします。
通常のいぶりがっこよりも塩分量を抑えてあるため、塩分の過剰摂取を心配せずにいぶりがっこを楽しめます。
近年は健康志向の高まりから各メーカーが様々な減塩商品を提供していますが、減塩タイプであっても全く塩分が含まれていないわけではないため食べる量には注意が必要です。
パッケージに記載されている栄養成分表示を確認し、ご自身の塩分摂取目標に合わせて選ぶようにしてください。
いぶりがっこに関するQ&A:素朴な疑問を解消!
いぶりがっこについて、もっと深く知りたい、こんな時はどうしたらいいの?
といった疑問を持たれている方のために、いぶりがっこを日々の食卓に取り入れる上でよくある質問とその答えをお伝えします。
-
Q1:いぶりがっこは毎日食べても大丈夫ですか?
いぶりがっこは健康に良い食品ですが、塩分が含まれているため毎日大量に食べるのは控えるのが賢明です。
少量でも満足感があるので他の食材と組み合わせたり間隔を空けて楽しんだりすることで、塩分の過剰摂取を心配せずに美味しく続けられます。 -
Q2:いぶりがっこは子供でも食べられますか?
はい、お子様でも食べられます。ただし、いぶりがっこ特有の燻製の香りと塩味が強いと感じるお子様もいるかもしれません。
細かく刻んでポテトサラダやチャーハンに混ぜたりマイルドなクリームチーズと合わせたりするなど、食べやすく工夫してあげると良いでしょう。 -
Q3:いぶりがっこの保存方法で気をつけることはありますか?
いぶりがっこは未開封であれば常温で保存できるものが多いですが開封後は冷蔵庫で保存し、なるべく早く食べきるようにしましょう。
空気に触れると風味が落ちやすくなるため、密閉容器に入れるかラップでしっかり包むのがおすすめです。 -
Q4:いぶりがっこはアレルギーの原因になることがありますか?
いぶりがっこは基本的に大根と米ぬか、塩、砂糖といったシンプルな材料で作られていますが、米ぬかを使用しているため米アレルギーのある方は注意が必要です。
また、製造過程で他の食品と同じラインを使用している可能性も考慮し、アレルギー表示を確認することをおすすめします。 -
Q5:いぶりがっこはどのように作られているのですか?
いぶりがっこは大根を燻製にした後、米ぬかや塩、砂糖などと一緒に漬け込み、じっくりと発酵させて作られます。
この燻製の工程が独特の香ばしい風味を生み出し発酵によって保存性と栄養価が高まります。地域や製造者によって製法に違いがあります。 -
Q6:いぶりがっこの「いぶり」とはどういう意味ですか?
「いぶり」とは、秋田の方言で「燻す(いぶす)」という意味です。文字通り大根を囲炉裏などの煙で燻すことから名付けられました。
この燻製によって、いぶりがっこならではの独特の香りと風味、そして保存性が生まれます。 -
Q7:いぶりがっこは妊娠中に食べても大丈夫ですか?
妊娠中にいぶりがっこを食べることは問題ありませんが塩分摂取量には注意が必要です。
むくみや高血圧のリスクを考慮し、他の食事とのバランスを取りながら少量を楽しむように心がけましょう。
心配な場合はかかりつけの医師に相談してください。 -
Q8:いぶりがっこは冷凍保存できますか?
いぶりがっこの冷凍保存は可能ですが解凍すると食感が多少変わることがあります。
風味が落ちることもあるためあまりおすすめはしません。
もし冷凍する場合は薄切りにしてラップで小分けにし、ジップロックなどに入れて保存すると良いでしょう。 -
Q9:いぶりがっこを使った面白いアレンジレシピはありますか?
いぶりがっこは和洋中問わず様々な料理にアレンジできます。
例えば、細かく刻んでタルタルソースに加えたり、オリーブオイルと合わせてパスタの具材にしたり、和風のピザのトッピングにしても美味しいです。
アイデア次第で楽しみ方が広がります。 -
Q10:いぶりがっこの他に、おすすめの発酵食品はありますか?
日本にはいぶりがっこの他にも健康に良い発酵食品がたくさんあります。
例えば、味噌、醤油、納豆、甘酒、ぬか漬け、キムチなどが挙げられます。
これらも腸内環境を整えたり栄養吸収を助けたりする効果が期待できるので、ぜひ食生活に取り入れてみてください。
いぶりがっこの栄養表示成分数値
※検査単位100g中
| エネルギー | 90kcal |
|---|---|
| タンパク質 | 1.3g |
| 脂質 | 0.2g |
| 炭水化物 | 20.7 |
| 食塩相当量 | 4.8g |
樽の味・漬物作業長のコメント

- 美味しいです!
- 今ではいぶりがっこを製造するメーカーも増えましたが、無添加でありながらここまで美味しいメーカーは大変めずらしいと思います。勿論食品添加物に頼らず商品化する事には数々の難題があります。しかし製造者の方が研究には研究を重ね商品化に成功したが故の美味しさです。お酒のあて、又はクリームチーズを付けて食べていただくと大変美味しいです。
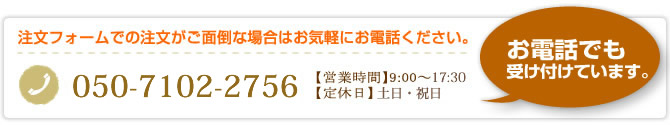
関連記事

- いぶりがっこってそもそもな~に?
- いぶりがっこの「がっこ」の意味や、いぶりがっこの香りや食感、どうやって作っているのかなどなど、いぶりがっこの「なに?」を紹介しています。